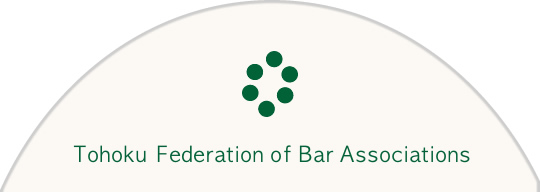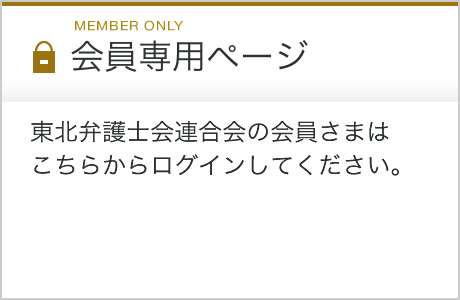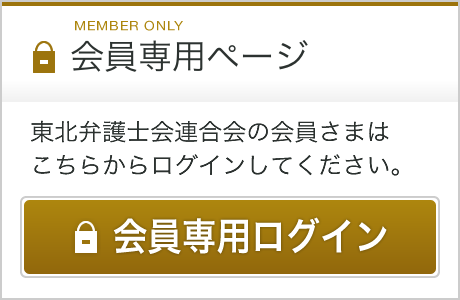刑事事件の再審制度は、人権擁護のために、誤判により有罪とされたえん罪被害者を救済することを目的とする制度である。裁判は人が行うものである以上、誤りは生じうる。だからこそ、最高裁は、白鳥決定(最高裁1975(昭和50)年5月20日決定)及び財田川決定(最高裁1976(昭和51)年10月12日決定)において、再審請求でも「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用されるとして、えん罪被害者の救済に向け積極的な姿勢を示したのである。
白鳥決定あるいは財田川決定以降、ここ東北地方においても、宮城県では松山事件について、誤判により一旦は死刑判決が確定したところ、再審により無罪判決がなされたこと、また青森県でも弘前事件、米谷事件について再審により無罪判決がなされたことが銘記されるべきである。
えん罪被害は、国家による最大の人権侵害の一つであり、えん罪被害者は迅速かつ確実に救済されなければならない。しかし現実には、再審は「開かずの門」と言われるほど、認められることがまれであり、現在の再審制度は、誤判からの救済手段としての意義・役割をほとんど果たせていないと言わざるを得ない。
本年(2024(令和6)年)5月に再審公判が結審し、同年9月に判決が言い渡される予定の袴田事件、また2023(令和5)年2月に即時抗告審で再審開始が維持されたものの、検察官の特別抗告により再審開始がなお争われている日野町事件の再審請求審においても、現行刑事訴訟法における再審に関する定め(再審法)の不備が改めて明らかになった。両事件を含む多くの事件では再審手続が長期化し、えん罪被害者の救済が遅々として進まないことの原因は、各事件固有の事情にあるものではなく、現在の再審制度が抱える制度的・構造的問題にあるというべきである。
すなわち、第一に、証拠開示制度が不備であることである。再審開始決定を得た事件の多くにおいては、再審請求手続の中で初めて開示された検察官の手持ち証拠の中に、再審開始を導く重要な証拠が含まれていた。このような事態は、そもそも有罪判決を言い渡した裁判が、果たして武器の対等という刑事裁判の基本的な原則が守られた公平かつ公正な裁判であったのかに強い疑問を抱かせるものである。その上、現行刑事訴訟法では、再審における証拠開示制度が整備されておらず、裁判所の裁量に委ねられているため、再審開始を導く重要な証拠が再審請求人に開示される保障がない。再審請求手続において十分な証拠開示制度を整備することが急務である。
第二に、検察官による不服申立が許容されていることである。近年、再審開始決定に対する検察官による即時抗告、特別抗告ないし異議申立が行われることが多く、その結果、袴田事件がまさにそうであったように、再審開始が遅延し、えん罪被害者の速やかな救済が阻害される事態が続いている。職権主義的審理構造のもとで、利益再審のみを認め、再審制度の目的をえん罪被害者の救済に純化した現行の再審請求手続においては、検察官は有罪立証をする当事者ではなく、「公益の代表者」として裁判所の審理に協力する立場に過ぎないのであるから、検察官に不服申立権を認める必要はない。
第三に、現行刑事訴訟法に再審請求審の手続規定、とりわけ手続の進行に関する明文の規定がないことである。そのため、審理の進行が各裁判所の裁量に委ねられ、ときに「再審格差」と呼ばれるような訴訟指揮における格差が問題とされてきた。加えて、再審手続において国選弁護制度はなく、適切な弁護を受ける権利の保障という観点からも手続規定の整備は不十分である。
よって、当連合会は、国に対し、えん罪被害者の迅速な救済を実現するため、以下の内容を含む再審手続に関する刑事訴訟法の各規定の適切かつ速やかな改正を求める。
1 再審請求手続における証拠開示の制度化
2 再審開始決定に対する検察官による不服申立の禁止
3 適正手続を保障する再審請求手続規定の整備
2024(令和6)年7月5日
東 北 弁 護 士 会 連 合 会
提 案 理 由
第1 はじめに
えん罪は国家による最大の人権侵害の一つである。
2023(令和5)年3月13日、東京高等裁判所第2刑事部は、袴田事件(1980(昭和55)年11月に強盗殺人罪・放火罪で死刑確定)の第2次再審請求について、2014(平成26)年3月27日に静岡地方裁判所がなした再審開始の決定を維持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。検察官はこの決定に対する特別抗告を断念し、再審公判が開始され、本年9月に判決が言い渡される予定である。袴田巌氏は、逮捕から約58年、死刑確定から約44年という時を経て、ようやく国家による人権侵害から救済されようとしている。
第2 再審をめぐる歴史
1 白鳥・財田川決定
再審において大きな意義を有するのは白鳥決定(最高裁1975(昭和50)年5月20日決定)及び財田川決定(最高裁1976(昭和51)年10月12日決定)である。
白鳥決定は、「法435条6号にいう『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いをいだかせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠をいうものと解すべきであるが、右の明らかな証拠であるかどうかは、もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中に提出されていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠を他の全証拠と総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと解すべきである。」と判示した。
また、財田川決定は、白鳥決定の上記判示を繰り返した上で、さらに「そして、この原則を具体的に適用するにあたっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであることを必要とし、かつ、これをもつて足りると解すべきであるから、犯罪の証明が十分でないことが明らかになった場合にも右の原則があてはまるのである。」と判示した(いずれも下線部は引用者による。)。
かように、白鳥決定・財田川決定は、再審請求においても「疑わしいときは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が適用されるとしたのである。
2 東北地方における再審事件
(1)弘前事件
青森県で発生した弘前事件について、1976(昭和51)年7月13日、仙台高等裁判所は再審の開始を決定した。
被告人とされた那須隆氏は、第1審で無罪判決を得たものの、控訴審で逆転有罪判決を受け、さらに上告棄却され、その後13年服役したのち、再審請求をなし、1977(昭和52)年に無罪判決が言い渡され確定し、雪冤を果たした。同事件は、白鳥決定後にはじめて最高裁で確定した判決について再審開始が認められた事例である。
(2)米谷事件
また、同じく青森県で発生した米谷事件についても、1976(昭和51)年10月30日、仙台高等裁判所は再審の開始を決定した。
被告人とされた米谷四郎氏は、青森地方裁判所における第1審で有罪判決を受け、その後10年服役したのち、再審請求をなし、1978(昭和53)年に無罪判決が言い渡され、雪冤を果たした。
(3)松山事件
そして、東北地方においては、いわゆる死刑4再審事件の1つである、宮城県で発生した松山事件について、被告人とされた斎藤幸夫氏の雪冤が果たされたことが特記されるべきである。
この事件は、1983(昭和58)年、検察官の即時抗告に対し、仙台高等裁判所が再審開始の原決定を維持し、1984(昭和59)年に再審において無罪判決が言い渡されたが、斎藤氏は、1955(昭和30)年末に逮捕され、再審開始決定によって死刑の執行が停止されるまで死の恐怖にさらされ続け、再審無罪判決まで身体拘束され、自由の身となったのは逮捕されてから29年が経過した後であった。
(4)このように、東北地方においても、えん罪により重大な人権侵害を被り、再審において雪冤を果たした人々が複数いることから、我々東北の弁護士も、改めて日本全国のえん罪被害者の救済のために、再審制度が十分に機能しなければならないとの思いを強くするものである。
3 近時の再審開始決定
近時、多くの再審開始決定がなされ、多くの被告人が雪冤を果たしている。
足利事件、布川事件、東京電力女性社員殺害事件、東住吉事件、松橋事件、湖東事件について再審開始決定がなされ、再審において無罪判決が言い渡され、確定している。
また、日野町事件については、大阪高等裁判所が再審開始を認めたものの、検察官が特別抗告しており未確定の状態にある。
冒頭に述べたように、袴田事件については、再審開始が確定し再審公判が開始されている。同事件の差戻し後の高裁決定では、再審請求手続の中で開示され提出された新証拠と、確定審で取り調べられた旧証拠とを総合評価し、白鳥決定及び財田川決定に沿う適切な判断手法をとったものであった。
第3 再審制度の問題点とその改正の必要性
1 明らかになった再審制度の問題点
しかし、袴田事件や日野町事件の再審請求審における審理を巡って、本来無辜の救済を目的とするはずの現行刑事訴訟法における再審に関する規定(再審法)の問題点が、改めて明らかになった。
すなわち、いずれの事件においても、即時抗告棄却決定まで長期間が要されており、また適正な証拠開示がなされず、検察官による不服申立がされているという点である。
2 審理の長期化
袴田事件の被告人とされた袴田巌氏は、2014(平成26)年3月27日静岡地方裁判所が再審開始とともに死刑及び拘置の執行停止を決定したことにより釈放されたものの、1980(昭和55)年11月19日に上告審で上告が棄却されて以来、40年以上にわたり死刑囚として生きることを強いられてきた。その苦痛は計り知れない。
このことについて、再審請求審の審理のあり方に関する規定がなく、各裁判所の裁量に委ねられていることが原因の一つといわなくてはならない。
すなわち、現行刑事訴訟法上、再審手続に関する規定は19箇条しか存在せず、再審手続の運用は個々の裁判体の裁量に大きく左右される。そのため、手続の運用が統一的になされておらず、再審請求人にとって「適正手続の保障」(憲法31条)がされているとは言えない状況にある。
ことに、現状においては、再審公判の前段階である再審請求審の手続が肥大化しており、再審請求審の手続に極めて長い年月を要している。このことは、再審請求人の「迅速な裁判を受ける権利」(憲法37条1項)をないがしろにしているものである。
かように、現行再審法は、憲法の要請をないがしろにしているともいうべきものなのである。
3 証拠開示規定の不存在
現行再審法においては、証拠開示に関する規定が存在しない。
松山事件においては、仙台地方裁判所古川支部の再審請求棄却決定について、仙台高等裁判所が差戻し決定をなした後に、多くの裁判不提出記録の証拠開示がなされ、いわゆる「平塚鑑定書」の存在などが明らかになったことが再審開始決定に結びついたものである。
袴田事件においても、第2次再審請求審において合計約600点もの裁判不提出記録が証拠開示され、その中に存在したボタンのタグの「B」という文字が、検察官が主張していた「サイズ」ではなく「色」を示す旨の製造業者の供述調書、いわゆる「5点の衣類」のネガフィルムなどが取り調べられた結果、再審開始が決定した。
かように、両事件とも、再審請求手続の中で、検察官の手持ち証拠が多数開示され、その中に再審開始を導く重要な証拠が含まれていたのである。適切な証拠開示がなされていれば、より早期の再審開始決定がなされたものと考えられる。
しかし、現在の刑事訴訟法では再審における証拠開示制度が整備されておらず、証拠開示が裁判所の裁量に委ねられているため、再審開始を導く重要な証拠が再審請求人に開示される保障はない。両事件において証拠開示が行われなければ、果たして再審開始決定がなされたのか疑問なしとしないが、これでは無辜の救済という再審制度の趣旨を実現できないこととなってしまう。
4 検察官による不服申立の許容
現行再審法においては、検察官による不服申立が認められている。これがえん罪被害者の迅速な救済を阻害するという問題は、かねてより指摘されてきた。そして、近年は布川事件、松橋事件、大崎事件、湖東事件及び日野町事件において、再審開始を認める即時抗告審決定について、検察官が最高裁判所に特別抗告をしている。その結果、特別抗告審の判断がなされるまで再審開始決定がなされないという事態が起き、迅速な救済が阻害されている(なお、大崎事件については特別抗告審において再審請求を棄却するという決定がされている)。
袴田事件においても、2014(平成26)年3月27日の静岡地方裁判所の再審開始決定について検察官が特別抗告しており、この抗告がなければ再審開始決定の確定が2023(令和5)年3月13日までずれ込むことはなかったのである。
憲法39条は「何人も・・・既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と「二重の危険」禁止原則を定める。最高裁判所は、「二重の危険」とは、同一の事件については訴訟手続の開始から終末に至るまでの一連の継続状態をいうものであるとし、検察官上訴制度が同条に違反するものではないとする(最高裁大法廷1950(昭和25)年9月27日判決・刑集4巻9号1805頁)。
しかし、現行刑事訴訟法は、再審制度を無辜の救済制度に純化させ、不利益再審を認めていない。かつ、「疑わしいときは被告人の利益に」の原則からは、いったん裁判所による無実を示す判断がなされた以上は、当該事件はすでに「疑わしい」ものとされたものというべきである。職権主義的審理構造のもと、再審手続において検察官は「公益の代表者」として裁判所が行う審理に協力する立場に過ぎないことに鑑みれば、検察官に、再審開始決定に対する不服申立権を認める必要はないというべきであって、法改正により直ちに禁止されるべきである。検察官が有罪であると主張するならば、それは再審公判で有罪立証を尽くせば済むことなのである。現に、再審公判が結審した袴田事件について、検察官は有罪立証を尽くし、死刑を求刑したところである。
5 審理手続に関する規定の整備等の必要性
以上述べたように、現行の再審手続にはその条文の少なさもあって、十分な手続的保障が定められているとは言えない。ゆえに、裁判所の裁量に委ねられる点が多く、審理が長期化することに加え、三者協議や事実取調べを全く行わないなど、十分な手続的保障がされているとは言えない事例も散見される。
また、大崎事件や日野町事件、飯塚事件等においては、通常審に関与した裁判官や過去の再審請求審に関与した裁判官が、当該事件の新たな再審請求審に関与していたことも明らかになっている。これは、裁判所の判断の公正さ・適正さを疑わしめるものである。
加えて、再審手続においては国選弁護制度がなく、資力がなく支援も得られないものは
・・・ 続きを読む最高裁判所大法廷(戸倉三郎裁判長)は、2024(令和6)年7月3日、旧優生保護法国家賠償請求訴訟において、旧優生保護法が憲法13条及び14条1項に違反することを認めた上で、国が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、権利の濫用として許されないとして、被害者に対する損害賠償を命じる判決を言い渡した(なお、唯一、除斥期間の適用が認められていた2023(令和5)年6月1日の仙台高等裁判所の判決については破棄した上で差し戻した。)。
本件は、15歳のときに優生手術を強制された宮城県在住の60代の女性が全国で初めて国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を仙台地方裁判所に提起し、その後の同種事件の先駆けとなった事件を含む全国5つの同種事件の上告審判決である。
1948(昭和23)年6月に制定された旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こと等を目的として、特定の障害ないし疾患を有するとされた者を一律に「不良」と断定し、1996(平成8)年に母体保護法に改正されるまでの約48年間、不妊手術約2万5000件、人工妊娠中絶約5万9000件、合計約8万4000件に及ぶ優生手術を強制した。
これまでも、2022(令和4)年2月22日に大阪高等裁判所が、同年3月11日に東京高等裁判所が、いずれも国に損害賠償を命ずる判決を言い渡し、その後も、2023(令和5)年3月16日の札幌高等裁判所、同月23日の大阪高等裁判所、同年10月25日の仙台高等裁判所、2024(令和6)年1月26日の大阪高等裁判所判決等、国に損害賠償を命じる判決が相次いで出されていた。
本判決は、最高裁判所として、旧優生保護法が憲法13条及び14条1項に違反すると明確に判断した。その上で、旧優生保護法の立法行為にかかる国の責任が極めて重大であること、被害者に国に対する損害賠償請求権の行使を期待することが極めて困難であったこと、適切な補償の措置が講じられてこなかったこと等に照らし、除斥期間の主張の要否に関する最高裁判例を変更した上で、国が除斥期間の主張をすることが信義則に反し、権利の濫用として許されないとした。これは、旧優生保護法による被害について除斥期間の適用を制限することについて統一的判断を示したものである。優生手術が極めて非人道的かつ差別的であり重大な人権侵害行為であることを直視し、除斥期間の適用を否定して国の賠償責任を認めたことは、人権保障の砦としての司法の役割を果たすものであり高く評価される。
もっとも、本件の背景にある旧優生保護法に基づく優生手術は、約8万4000件に及ぶにもかかわらず、全国において国家賠償訴訟の提起に至った被害者はわずか39名に過ぎない。旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金の支給認定の状況についても令和6年5月末時点で1100件が認定されたにとどまり、大多数の被害者は様々な理由により未だ声を上げられない状態が続いている。そして、被害者の多くは高齢となっており、既に亡くなられた方も少なくない。
このため、訴訟提起に至った被害者のみならず優生手術のすべての被害者に対し、一日も早く本判決の趣旨を踏まえた全面的な謝罪と速やかな被害回復が図られることが必須である。
よって、当連合会は、国に対し、本判決を受けて、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を行うことを強く求めるものである。
2024(令和6)年7月4日
東 北 弁 護 士 会 連 合 会
会 長 竹 本 真 紀
1 政府は、2024年2月27日、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(以下「本法案」という。)を国会に提出し、本法案は、一部修正の上、同年4月9日に衆議院を通過し、同年5月10日の参議院本会議で可決成立した。
本法案の概要は、①重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものを、重要経済安保情報として秘密指定する(特別防衛秘密及び特定秘密に該当する情報を除く)、②重要経済安保情報を漏洩した者と不正に取得した第三者を、最高5年の拘禁刑に処す、③重要経済安保情報を取り扱う業務は、適性評価により、重要経済安保情報を漏洩するおそれがないと認められた者に制限する、というものである。これは、特定秘密保護法を経済安全保障分野に拡大しようとするものであるが、本法案には以下に指摘するとおり、憲法上重大な問題がある。
2 まず、本法案には、特定秘密保護法と同様の憲法上の重大な問題がある。
(1)すなわち、特定秘密保護法同様、この法律には、まず、情報の非公開を広範に許容してしまうものである点で、国民の知る権利を不当に制限し、国民主権の原理が脅かされるという問題がある。また、処罰範囲が広範かつ不明確であるうえ、対象となる特定秘密の内容が明かされないまま刑罰が科されるおそれがあり、被告人の防御の機会が奪われかねない。さらに、同法律の定める適性評価制度は、評価対象者の精神疾患や信用情報をも調査事項とするものであり、評価対象者のプライバシーを侵害する危険性が高く、また、適性評価の名の下に評価対象者の思想調査がなされるおそれもあり、思想信条の自由を侵害する危険もある。
当連合会は、2013年3月30日及び同年11月25日に、このような憲法上重大な問題をいくつも抱える特定秘密保護法の制定に反対する会長声明を発し、更に2014年7月4日には同法の廃止を求める決議を採択して、一貫して同法に反対してきた。
(2)また、国連の自由権規約委員会においても、第6回(2014年)及び第7回(2022年)の日本政府報告書審査で、特定秘密保護法について、①特定秘密の対象となる情報カテゴリーを明確にすること、②国家の安全という抽象的な概念により表現の自由を制約するのではなく自由権規約第19条第3項に則った制約となるようにすること、③公共の利益に関する情報を流布することにより個人が処罰されないことを保障することを、政府に求め続けてきている。
(3)しかしながら、今日まで、政府において上記のような同法の問題点を払拭しようという姿勢は全く見られないまま、今般、同法を経済安全保障分野に拡大する性質を有する本法案が国会に提出され、本法案提出からわずか1ヶ月と10日という短期間で衆議院を通過した。そして、衆議院通過から約1ヶ月という短期間で、十分な審議による問題点の解消すらなされずに参議院で可決成立するに至っている。なお、可決された修正案においては、重要経済安保情報の運用状況について国会に報告するものと修正されているが、これは、特定秘密保護法には規定がありながら同法案になかったものを加えたものであり、特定秘密保護法並みになっただけであって、特定秘密保護法の問題点を払拭するものではない。
3 さらに、以下のとおり、本法案には特定秘密保護法を上回る問題がある。
まず、秘密指定される重要経済安保情報の範囲は抽象的で、極めて広範かつ不明確である。政府が作成した本法案の解説では、「経済安全保障上の重要な情報」のうち、漏洩等があることで「著しい支障」が生じるものを「特定秘密」とし、それには至らない「支障」相当のものを「重要経済安保情報」として区分したうえで、本法案は後者の「重要経済安保情報」を対象とするものとされているが、特定秘密保護法のように外交・防衛・テロ・スパイ活動の4分野に限定されているわけでもなく、特定秘密保護法以上に対象範囲が広範かつ不明確といわざるを得ず、これでは「重要経済安保情報」が恣意的に拡大される懸念がある。
また、特定秘密保護法の適性評価は主に公務員が対象であったが、本法案では広範な民間事業者や大学、研究機関等も対象とされ、当事者のみならず家族や同居人も対象とされるなど、対象範囲が極めて広い。調査内容も、精神疾患に関する事項や経済状況等も含む広範かつ私事性・秘匿性の高い高度なプライバシー事項が対象とされている。その結果、内閣総理大臣の下に設けられる新たな情報機関に適性評価対象者の膨大な情報が蓄積されることとなるが、適性評価のための調査の行き過ぎを抑止するための仕組みも想定されていないようであり、プライバシー保障の観点から疑問がある。
4 結語
以上述べてきたとおり、本法案についても、憲法上の重大な問題が複数あることは、特定秘密保護法と全く同様である。また、本法案は、同法以上に対象範囲が広範かつ不明確であり、秘密が恣意的に拡大するおそれがより高いと言わざるを得ない。同法の抱える憲法上の重大な問題を何ら改善しないまま、拙速な審議で本法案を可決成立させたことに、当連合会は強く抗議するとともに、今後、政府に対しては、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」により、国民の権利が不当に制限されることのないよう強く求める。
2024(令和6)年5月11日
東北弁護士会連合会
会 長 竹 本 真 紀
政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法案(以下「改正案」という。)を閣議決定し、国会に提出した。今般の改正案は、第14章として「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と普通地方公共団体との関係等の特例」を新設し、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律上の根拠がなくても、国が地方公共団体に対して必要な指示を行うことができることなどを定めた特例を新設するというものである。
2000年に施行された、いわゆる地方分権一括法(以下「地方分権一括法」という。)によって、国と地方公共団体との関係は「対等協力」の関係とされた。そして、地方自治法では、国の地方公共団体に対する関与の類型を、法定受託事務と自治事務で区別して、法定受託事務については、国の指示権を一般的に認めるのに対し、自治事務については、地方公共団体の自主性を尊重する観点から、「国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合」(地方自治法第245条の3第6項)に限って、個別法で根拠規定を設けることとされた。
このように、現行地方自治法は、自治事務に関する国の関与を限定することにより、地方公共団体の自主的・自立的な事務執行、ひいては憲法上の制度である地方自治の実効性を担保しようとしている。
しかし、改正案においては、個別法の根拠規定なしに、国の自治事務に関する指示権を一般的に認めようとするものであり、地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。
また、現行地方自治法では、個別法で自治事務に対する指示権を認めることとする場合の要件として、「国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合」(同法第245条の3第6項)とされているにもかかわらず、改正案では、「緊急に」との文言がなく、恣意的な運用がなされるおそれも否定できない。
政府は、大規模災害及びコロナ禍を例として取り上げて、国の指示権を認めるべきとするが、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに一般法である地方自治法を改正する必要性があるのかは疑問であり、立法事実は存在しない。そもそも、自然災害や感染症への対応については、刻一刻と変化する現場の状況に応じて迅速に対策を検討・実施することが求められるところ、そのような検討に必要な情報を有しているのは、国ではなく、むしろ現場で事態に直面している地方公共団体である。当連合会に所属している、東日本大震災の被災経験がある各地の弁護士会は、被災者支援活動等を通じて、被災者の救済に何より必要なのは、国に権力を集中させるための法制度を新設することよりも、むしろ、事前の災害対策を十分に行うことであると理解している。このことは、日本弁護士連合会が2015年9月に東日本大震災の被災三県の37市町村に対して実施したアンケート(24市町村から回答)の中で、「災害対策・災害対応について市町村と国の役割分担はどうすべきか」との質問に対して、約8割の自治体である19自治体が「市町村主導」と回答していることにも表れている。
これらの事情に鑑みれば、大規模災害や広範囲に及ぶ感染症のまん延の際に、国に求められるのは、地方公共団体から寄せられる多数の現場情報の収集及び整理・共有、対応にあたる地方公共団体への後方支援などである。自治事務に関する国の指示権を一般的に認めることは、むしろ災害や感染症等に対する現場対応の混乱を招くおそれがある。
以上の理由から、当連合会は、東日本大震災において甚大な被害を受けた被災地の弁護士会連合会として、改正案に反対するものであり、政府に対し、改正案の国会提出に抗議するとともに、国会に対し、地方自治の理念をふまえた慎重な審議を求める。
2024年(令和6)年5月11日
東北弁護士会連合会
会 長 竹 本 真 紀
1 2023年10月7日、ハマス等パレスチナ武装勢力によるイスラエルへの武力攻撃が行われ、それ以降、ガザ地区において深刻な戦闘状態が継続している。
ハマス等の攻撃によるイスラエル側の死者数は1200人を超えたとされ、約30人の子どもを含む240人を超えるイスラエル市民及び外国人が人質にされ、現在も多数が解放されていない。
他方、この間、イスラエルからの攻撃により、ガザ地区でのパレスチナ側の死者数は2万6400人を超え、負傷者数は6万5000人を超えたと報道されている(ガザ地区保健省2024年1月28日発表)。これらガザ地区における死傷者のうちの70%は女性及び子どもであるとみられ、1万人以上の子どもが死亡し、1000人以上の子どもが片足又は両足を失い、そのほとんどが麻酔なしで切断されたと報告されている(国際NGOセーブ・ザ・チルドレン2024年1月11日発表)。攻撃の対象は病院や学校にも及び、少なくとも250人を超える医療従事者が犠牲になったとされる。ガザ地区の住民は、水や電気の供給も遮断されて、避難移動することを余儀なくされ、さらに移動先の環境も劣悪で医療や生活に必要な物資も不足している。
2 ハマス等パレスチナ武装勢力が市民を巻き込んだ攻撃によりイスラエル側に多くの犠牲を出したこと及び一般市民の人質をいまだに解放しないことは、国際人道法に反する違法行為である。
他方、イスラエルがガザ地区に対し市民の住居や文民病院を含む無差別攻撃を継続し、これによって子どもや医療従事者を含む多数の一般市民の死傷者を出し、住民に強制移動を余儀なくさせていることは、看過できない国際人道法違反の行為である。
3 このようなイスラエル・ガザ地区での深刻な人道状況を受けて、2023年12月12日、国連総会臨時特別会合において、人道上の即時停戦、国際人道法を含む国際法上の義務(特に文民保護)の遵守、すべての人質の無条件即時解放、人道的アクセス確保を求める総会決議が採択された。また、同月23日に国連安全保障理事会(安保理)において、ガザ地区に対する人道支援の拡大と監視に関する安保理決議第2720号が採択された。
4 東北弁護士会連合会は、犠牲となったすべての方々に哀悼の意を表し、ガザ地区における即時停戦と平和的解決を心から願うとともに、国連はじめ平和的解決に向けて尽力されている方々に連帯の意思を表明する。また、日本国憲法の「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」との理念を実現すべき日本国政府に対し、ガザ地区における即時停戦、人質の解放、人道危機の解消を目指して外交努力を尽くすよう求める。
2024年(令和6年)2月2日
東北弁護士会連合会
会 長 虻 川 高 範
1 仙台高等裁判所第2民事部(小林久起裁判長)は、2023(令和5)年10月25日、旧優生保護法に基づく優生手術を強制された被害者に対し損害賠償を命じた原審仙台地方裁判所の判決(本年3月6日)に対する控訴人(国)の控訴を棄却する判決を言い渡した。
本判決は、原判決に引き続き、旧優生保護法が、立法当時から、憲法13条、14条1項、24条2項に明白に違反することを認めた。その上で、国が違法な立法を行った上、それに基づく政策を継続し、差別や偏見を固定化することによって、被害者が損害賠償請求権を行使することを著しく困難にさせたと認め、このような重大な人権侵害の政策を推進してきた国が被害者の損害賠償権の消滅を主張することは、正義・公平の観点からも、権利の濫用として許されない、と判断し、被害者の請求を認めたものである。
2 これまでも、2022(令和4)年2月22日に大阪高等裁判所、同年3月11日に東京高等裁判所、そして、2023年(令和5年)3月16日に札幌高等裁判所が、いずれも国に損害賠償を命ずる判決を下し、また、各地方裁判所においても、熊本地方裁判所、静岡地方裁判所、そして本件の原審仙台地方裁判所も、それぞれ国に損害賠償を命ずる判決を下してきた。
3 この度の仙台高等裁判所の判決は、これらの多くの全国の裁判例と同様に、被害者の請求を認めたものである上、さらに旧優生保護法の違憲性を一層明確に認め、重大な人権侵害を行なってきた国が被害者の請求権の消滅を主張するのは権利の濫用として許されないと明確に判断した点において、高く評価できるところであり、本判決及びここに至るまでの上記判決の集積によって、長年にわたり重大な人権侵害を受けてきた旧優生保護法の被害者に対し、消滅時効や除斥期間の適用を制限すべきであるとの司法の判断は、大方固まったと言うべきである。また、本判決が、優生手術を受けた上に提訴に至るまでの長年の精神的苦痛を全体として評価し、一時金支給法で定められた一時金の額320万円を大幅に上回る額の慰謝料を認めたことからも、同法による救済が不十分であったことが一層明らかになったところである。
4 したがって、当連合会は、国に対し、本判決に対して上告せず一刻も早く本判決を確定させて被害者を救済することを求めるとともに、改めて一時金支給法を抜本的に見直し全ての被害者に対して被害を償うに足りる補償金を支払い、被害者救済のための制度を確立することを強く求めるものである。
2023年(令和5年)10月30日
東北弁護士会連合会
会 長 虻 川 高 範
えん罪は国家による最大の人権侵害の一つであり、起きてはならないことであるが、万が一、えん罪が起きてしまったときは、えん罪被害者は速やかにかつ確実に救済されなければならない。しかし、えん罪被害者の救済手段となるはずの刑事事件の再審制度は、「開かずの扉」とも言われるほど、再審が認められることがまれであり、えん罪被害者の救済は遅々として進まない状況にある。現在の再審制度は、えん罪被害者の救済手段としての意義・役割を十分に果たせていないと言わざるを得ない。
21世紀に入って以降、足利事件、布川事件、東京電力女性社員殺害事件、東住吉事件、松橋事件、湖東事件の6事件で再審により無罪判決が確定し、さらに、本年(2023年(令和5年))に入ってからも袴田事件について再審開始決定が確定するなど、近年、再審をめぐる動きは活発化している。
しかし、現行刑事訴訟法では、再審手続に関する規定が旧刑事訴訟法から内容を引き継いだ19か条しかなく(刑事訴訟法435条ないし453条)、とりわけ再審請求手続における審理の在り方については、刑事訴訟法445条において、事実の取調べを受命裁判官又は受託裁判官によって行うことができる旨が定められているだけで、裁判所の広範な裁量に委ねられている。そのため、再審請求事件の審理の進め方は裁判所によって区々であり、再審をめぐる動きが活発化する中で、いわゆる「再審格差」と呼ばれる裁判所ごとの格差が目に見える形で現れるようになり、制度及び規定の不備が看過できないものであることが明らかとなっている。
その中でも、とりわけ大きな問題となっているのが、再審における証拠開示制度の不備である。再審開始決定を得た事件の多くにおいて、再審請求手続の中で初めて開示された検察官の手持ち証拠の中に、再審開始を導く重要な証拠が含まれていた。これは、再審請求手続における証拠開示の重要性を端的に示すものである。
しかし、現行刑事訴訟法には再審における証拠開示について定めた明文の規定は存在せず、裁判所の訴訟指揮に基づいて証拠開示が行われる。証拠開示が裁判所の裁量に委ねられることから、再審開始を導く重要な証拠が再審請求人に開示される保証はない。
えん罪被害者の救済という再審の理念を実現するためには、再審請求手続において証拠開示が十分に行われ、通常審段階で公判に提出されなかった裁判所不提出記録を再審請求人に利用させることが不可欠であり、再審請求手続における証拠開示制度の整備が急務である。
また、再審開始決定に対して検察官の不服申立てが許容されていることも看過できない問題である。再審開始決定に対する検察官の不服申立てが、えん罪被害者の速やかな救済を阻害していることはかねてより指摘されている。近時の再審開始決定を得た事件の多くにおいて、再審開始を認める即時抗告審の決定に対し、検察官が最高裁判所に特別抗告を行っており、えん罪被害者の救済が長期化することにつながっている。このように、検察官の不服申立てが許容されていることによる弊害は顕著であり、速やかに是正する必要性が高い。
このような点を踏まえ、当連合会は、えん罪被害者を速やかに、かつ、確実に救済するため、国に対し、再審請求手続における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止、及び、再審請求手続における手続規定の整備を中心とする再審法の抜本的な改正を速やかに行うよう求める。
2023年(令和5年)9月9日
東北弁護士会連合会
会 長 虻 川 高 範
仙台高等裁判所・仙台簡易裁判所判事の岡口基一裁判官(以下「岡口裁判官」という。)は、性犯罪についてSNS・記者会見・ブログ・週刊誌のインタビューで発言したこと、犬の返還を求める訴訟についてSNS及びブログで発言したことを理由として、2021(令和3)年6月に裁判官弾劾裁判所に訴追され、現在、同裁判所での審理が進められている。一方、岡口裁判官は、同年7月、同裁判所から、裁判官弾劾法(以下「法」という。)39条により、職務停止決定が出され、現在まで2年以上も裁判官としての職務が停止されている。
憲法は、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」(76条3項)と定め、裁判官の職権行使の独立を明記するとともに、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」(78条前段)として裁判官の身分を強く保障している。これは、司法による権利救済・人権擁護が他の権力からの影響を受けずに行うことができるためは、「司法の独立」を制度的に保障し、憲法の根本原理である三権分立を具体化し、もって、国民の人権保障を全うするためとされている。
これを受けて裁判官弾劾法も、罷免事由を「その他職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」(法2条2号)と定め、懲戒事由としての「品位を辱める行状」(裁判所法49条)と比較しても、罷免事由を極めて限定している。
裁判官の罷免事由が厳しく限定されているのは、司法権とは別の国家機関である国会議員の裁判員によることから、弾劾裁判が安易に行われれば、司法権の独立を犯しかねないからである。また、罷免が裁判官から法曹資格すら失わせる重大な効力を有するからでもある。このため、過去に弾劾裁判所に訴追された9件のうち罷免の判決がされた7件は、収賄や公務員職権濫用、児童買春、ストーカー行為、盗撮等の犯罪行為に該当する事案であり、いずれも犯罪行為又はそれに匹敵する著しい不正行為に及んだものばかりで、司法権の独立、裁判官の身分保障への懸念もない事案であった。
これに対して、本件訴追は、本件投稿等、岡口裁判官の私的な表現行為を理由とするもので、過去の罷免事例とは著しく事案を異にしている。
表現の自由は、何人にも保障される重要な人権であり(憲法21条1項)、その保障は裁判官にも及び、裁判官も一市民として表現の自由を有する。仮に、裁判官の表現行為を理由に罷免の裁判がなされた場合には、裁判官の一市民としての表現活動に強い萎縮効果をもたらすほか、裁判官の身分保障(憲法78条)、ひいては裁判官の独立(憲法76条3項)に対する重大な脅威となり、三権分立のバランスを崩す契機となりかねない。したがって、表現行為を理由に罷免という重大な結果をもたらすには、それに見合うだけの重大な違法性が存在しなければならない。
確かに、本件訴追の対象となる投稿等の中には、被害者遺族の感情を傷つけるなど不適切と評価されうる内容もある。また、この投稿の一部については、遺族からの損害賠償請求訴訟の一審判決において、「(遺族に対する)侮辱的表現であって、原告らの名誉感情をその受任限度を超えて侵害するもの」と認定され、慰謝料請求が認められてもいる。このため、岡口裁判官のこれらの行為について、懲戒事由としての「品位を辱める行状」(裁判所法49条)に該当するとも考えられる。しかし、これらの行為が、過去に罷免されたような、犯罪行為又はそれに匹敵する著しい不正行為に該当するとは認められない。したがって、裁判官の職を失わせ、法曹資格さえも失わせるほど重大な非違行為である「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に該当するとは言えないものである。
よって、当連合会は、本件訴追が、司法権の独立と表現の自由の保障など、憲法上極めて重大な問題を有していることから、現在、弾劾裁判の審理をしている裁判官弾劾裁判所に対し、慎重な審理を行い、罷免事由を厳格に解釈して、岡口裁判官を罷免しないとする裁判をされるよう求める。
2023年(令和5年)9月9日 東北弁護士会連合会 会 長 虻 川 高 範
- 2024-07-09New

- 再審法の速やかな改正を求める決議New
- 2024-07-09New

- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議New
- 2024-07-08New

- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明New
- 2024-05-15

- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15

- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05

- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13

- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13

- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11

- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議
- 2023-07-11

- 地域社会や自然環境・景観と調和した再生可能エネルギーの導入のために、 住民等の意見が適切に反映される制度の拡充を求める決議
- 2023-07-10

- オンライン接見の法制度化を求める会長声明
- 2023-06-12

- トランスジェンダーの弁護士に対する殺害予告に断固抗議し、性的マイノリティに対する差別の根絶を目指す会長声明
- 2023-06-12

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟判決を受けて、国に対し、全ての被害者に対する謝罪と速やかな被害回復措置を求める会長声明
- 2023-03-23

- 入管法改正案の提出に強く抗議する会長声明
- 2023-03-23

- 敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有及びその行使のための準備を進めることに強く反対する会長声明
- 2023-02-13

- 日本弁護士連合会及び最高裁判所に対し、地域司法の基盤整備に関する協議を直ちに再開するよう求める会長声明
- 2022-09-15

- 自然災害債務整理ガイドライン・コロナ特則の改定等を求める会長声明
- 2022-07-08

- 地方裁判所支部における民事裁判手続IT化の運用開始にあたり改めて地域の司法基盤の充実を求める決議
- 2022-07-08

- 改めて、国に対し、犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
- 2022-04-08

- ロシア連邦のウクライナへの軍事侵攻を強く非難する会長声明
- 2022-03-18

- 東京電力福島第一原子力発電所事故被害者の損害賠償請求集団訴訟の判決確定を受け、あらためて原子力損害賠償にかかる中間指針の改訂を求める会長声明
- 2021-12-23

- 中間指針の改定、被災者の生活再建を支える立法、及び、被災者への差別防止施策を求める決議
- 2021-12-23

- すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議
- 2021-03-17

- 少年法改正に反対する会長声明
- 2021-03-16

- 災害援護資金貸付に関する要請書
- 2020-10-30

- 日本学術会議会員の任命拒否に対する会長声明
- 2020-05-15

- 東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定の撤回を改めて求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法改正案に反対する会長声明
- 2020-03-16

- 原発事故損害賠償請求権の時効消滅に対応するための立法措置を求める会長声明
- 2020-03-16

- 東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明
- 2019-10-25

- 令和元年台風19号による被害に関する会長声明
- 2019-07-12

- 被災者支援のために「災害ケースマネジメント」の制度化に向けた法改正等を求める決議
- 2019-07-12

- 裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2019-07-12

- 新屋演習場へのイージス・アショア配備に反対する会長声明
- 2019-07-12

- 旧優生保護法による被害の全面回復を求める会長声明
- 2019-04-11

- 改めて少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
- 2018-07-13

- 成年後見制度利用促進のための多職種による広域的な連携協働体制の整備及び経済的支援の拡充を求める決議
- 2018-07-13

- 憲法改正国民投票法を抜本的に改正することを求める決議
- 2017-07-10

- 日本国憲法施行70年にあたり、日本国憲法の基本原理及び立憲主義の堅持を求める決議
- 2017-07-10

- 生活困窮者自立支援制度の改善を求める決議
- 2017-05-15

- 震災特例法の再延長等を求める要望書
- 2017-03-21

- いわゆる「共謀罪」法案に反対する会長声明
- 2016-07-01

- 犯罪加害者家族に対する支援を求める決議
- 2016-07-01

- 地域司法の基盤整備に関する協議結果を受けて、改めて裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2016-07-01

- 消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの地方移転に反対する決議
- 2016-02-09

- 夫婦同氏の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明
- 2015-09-26

- 安全保障関連法案の採決強行に抗議する会長声明
- 2015-09-26

- 少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
- 2015-07-03

- 憲法違反である「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」 の国会提出に抗議し、その廃案を求める決議
- 2015-07-03

- 裁判所支部管内における司法機能の整備・拡充を求める決議
- 2015-07-03

- 「自然エネルギー100%」による持続可能なエネルギー社会実現に向けた施策を求める決議
- 2015-07-02

- 共謀罪の新設に反対する会長声明
- 2015-05-16

- 災害対策を理由とする国家緊急権の創設に反対する会長声明
- 2014-12-06

- 商品先物取引における不招請勧誘禁止規制緩和策に反対する会長声明
- 2014-09-27

- 裁判所関連予算の大幅増額を求める会長声明
- 2014-07-04

- 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し その即時撤回を求める決議
- 2014-07-04

- 特定秘密の保護に関する法律の廃止を強く求める決議
- 2014-07-03

- 「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの 業務の特例に関する法律」の有効期限の延長を求める要望書
- 2014-06-07

- 法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会「事務当局試案」に関する会長声明
- 2014-05-10

- 「通信傍受の合理化・効率化」に反対する会長声明
- 2014-03-22

- 復興事業用地の確保にかかる特例法の制定を求める要望書
- 2013-11-25

- 特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明
- 2013-07-05

- 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償請求権の 消滅時効に関し特別の立法措置を求める決議
- 2013-07-05

- 被災地の復興を促進するため、新たな法制度及び制度の改正・改善を求める決議
- 2013-06-08

- 被災ローン減免制度の不当な運用の改善を求める会長声明
- 2013-03-30

- 秘密保全法制の制定に反対する会長声明
- 2013-03-30

- 普天間飛行場へのオスプレイの配備撤回及び国内におけるオスプレイの 飛行の全面中止を求める会長声明
- 2013-02-08

- 東京電力株式会社の福島第一原子力発電所事故による 損害賠償の消滅時効の取扱についての会長声明
- 2012-07-06

- 個人保証の原則的な廃止等を求める決議
- 2012-07-06

- すべての裁判所支部管内における司法の機能充実を求める決議
- 2012-07-06

- 原子力発電と核燃料サイクルの廃止を求める決議
- 2012-06-27

- 大飯原子力発電所再稼働決定の撤回等を求める会長声明
- 2012-02-03

- 東日本大震災の被災者への「法的支援事業」特別措置法 の制定を求める会長声明
- 2011-12-03

- 各種人権条約に基づく個人通報制度の早期導入等を求める決議
- 2011-10-01

- 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介手続を 各地で実施するよう求める会長声明
- 2011-07-08

- 福島第一原子力発電所事故を早急に収束させ、住民の安全を確保し、汚染地域の原状回復等を求める決議
- 2011-07-08

- 東日本大震災の被災者救済と被災地の復旧・復興を求める決議
- 2011-07-08

- 日本国籍を有しない者の調停委員任命を求める決議
- 2011-07-08

- 暴力による弁護士活動への妨害行為に対し断固として立ち向かうことを誓うとともに、秋田における弁護士刺殺事件での警察の対応について徹底した調査・検証を求める決議
- 2011-06-04

- 被災者の信用情報の取扱について|2011(平成23)年6月4日東北弁護士会連合会
- 2011-05-21

- 権利保全特別措置法第6条の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
- 2011-05-21

- 東日本大震災への罹災都市借地借家臨時処理法の適用に関する意見書|2011(平成23)年5月21日東北弁護士会連合会
- 2010-11-04

- 秋田弁護士会所属弁護士の殺害事件に関する会長声明
- 2010-07-02

- 司法修習生に給与を支給する制度の継続を求める決議
- 2010-07-02

- えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議
- 2010-07-01

- 国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明
- 2009-07-03

- 地方消費者行政の充実を求める決議
- 2009-07-03

- 緊急貧困対策、労働法制の抜本的改正及びセーフティネットの再構築を求める決議
- 2009-04-04

- 取調べの可視化(取調べの全過程の録画)を求める会長声明
- 2009-02-13

- 裁判員制度の実施にあたって留意すべき問題点に関する意見書|2009(平成21)年2月13日東北弁護士会連合会