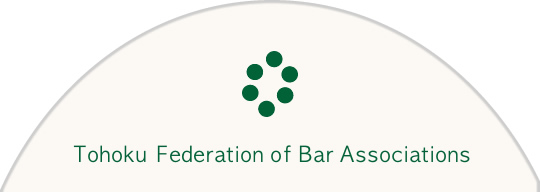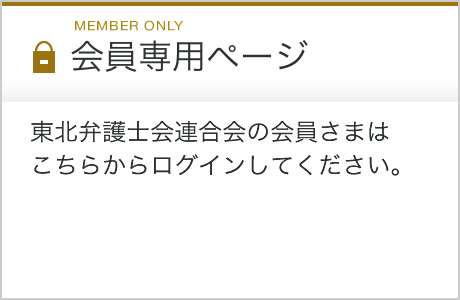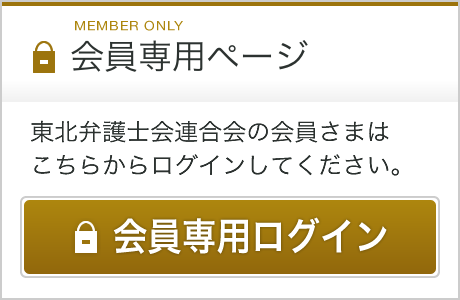昨年3月11日に発生した東日本大震災の被災地においては,今なお,宅地や建物の損壊に伴う二重ローン,就業先からの解雇,借金の相続等の様々な法的問題を抱えた被災者が生活している。さらに原子力発電所事故による被害者の法的対応の需要は,20万件以上にも達すると想定されている。
当連合会管内の各単位弁護士会,日本弁護士連合会,日本司法支援センター(法テラス)等は,震災直後から,被災地における法的ニーズに応えるべく法律相談を実施してきた。被災者の多くは,震災により経済的な損害を被っており,生活に困窮している者も相当な数に上ることから,法的な対応をするにあたっては,総合法律支援法に基づく法的支援が期待される。しかし,現在の,総合法律支援法に基づく被災地での法的支援には,大きな限界が存在する。
総合法律支援法は,裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに,弁護士・司法書士等のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施等について定め,資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用を容易にする民事法律扶助事業を中核の事業の一つとしている。
この民事法律扶助事業においては,利用のための資力要件が課されているが,震災,津波,原発事故の被災地において,法律問題を抱えた者に対し,資力の有無を申告させ確認することは,被災者の苦しみへの配慮を欠くことになりかねない。また,一定額の地震保険金等が支払われてそれを保有している場合には,資力要件を満たさないとされ,やむを得ない出費予定を証明しないと民事法律扶助を利用できない運用となっているが,このような運用は,法的救済を必要とする被災者に過度の制限や負担を課すものである。
さらに,民事法律扶助事業による法的支援が受けられたとしても,多大な経済的な損害を被っている被災者にとっては,事件が解決した後の弁護士報酬・実費等の償還が大きな負担となりかねない。
その上,今回の東日本大震災の被災地においては,「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」「震災ADR」等の,裁判外の法的問題の解決手続が設けられているが,民事法律扶助事業の適用は,民事裁判等手続(裁判所における民事事件,家事事件,行政事件に関する手続や示談交渉等)に限定されており,被災地における裁判外の手続を直接の援助対象として認めていない。
そこで,当連合会は,東日本大震災及び原子力発電所事故の被災者支援のために,
(1)資力で被災者を選別しない法的支援事業の創設
(2)報酬・実費等にかかる償還免除及び支払猶予
(3)上記民事裁判等手続に限定されない柔軟な支援の実現
などを内容とする「法的支援事業」特別措置法の制定を求める。
国は,現在会期中の通常国会において,速やかに本特別措置法を制定し,被災地において,被災者が一日も早く経済的不安なく法的手続の支援を受けられる環境を整えるべきである。
2012年(平成24年)2月3日
東北弁護士会連合会
会長 廣嶋清則
- 2024-07-09New

- 再審法の速やかな改正を求める決議New
- 2024-07-09New

- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議New
- 2024-07-08New

- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明New
- 2024-05-15

- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15

- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05

- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13

- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13

- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11

- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議