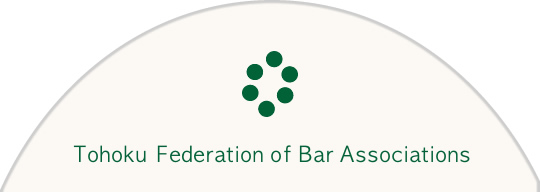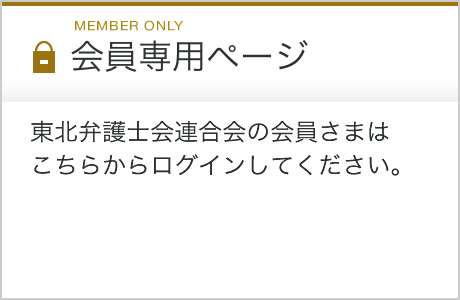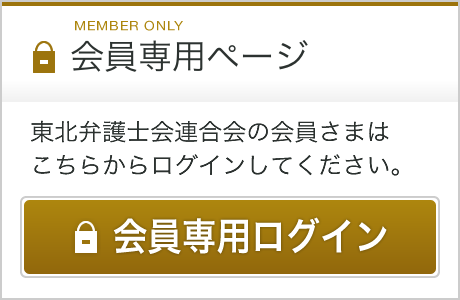少年鑑別所での心身鑑別が必要と判断されて観護措置決定により身体を拘束された少年については,事件の軽重を問わず,その生育歴・家庭環境にも大きな問題を抱えたケースが多く,また,少年院送致などの重大な処分を受ける可能性も高い。
弁護士付添人は,少年審判において非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう,少年の立場から手続に関与し,家庭や学校・職場等少年を取りまく環境の調整を行い,少年の立ち直りを支援する活動を行っているが,現状では,観護措置総数に対して弁護士が国選付添人に選任された事件の比率は,全国で約5.5%(2009年),東北六県ではわずか約4.1%にとどまる。これは,現在の国選付添人制度が,対象事件を重大事件に限定し,かつ,家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ裁量で付添人を付すことができる制度だからである。昨年5月21日からは,被疑者段階の国選弁護制度の対象が窃盗や傷害などの事件にまで拡大されたが,これにより,少年の場合には,「捜査の段階では国選弁護人が選任されたにもかかわらず,家庭裁判所の審判になると国選付添人が選任されない」という事態が生じうる状況となっており,制度上の矛盾は明らかである。
こうした問題状況を受け,日本弁護士連合会は,費用を負担する資力のない少年やその保護者のために弁護士の私財により付添人費用を援助する制度(少年保護事件付添援助制度)を実施してきた。加えて,東北六県では,弁護士派遣制度を設け,多くの会員が同制度に協力し,各県1か所しかない少年鑑別所との物理的距離や冬季の積雪という悪環境にもかかわらず献身的努力を継続している。また,少年事件の場合,身体拘束地の家庭裁判所から住所地の家庭裁判所に移送されるケースが多いことから,移送先の弁護士会に所属する弁護士ができるかぎり付添人活動を引き継ぐという連携も図られつつある。
その結果,東北六県の観護措置総数に対し弁護士付添人が選任された事件の比率は全国水準を上回る61.1%となっている。
しかし,わが国が批准している子どもの権利条約37条(d)に照らせば,付添人制度の実現は,本来国の責務であり,少年保護事件付添援助制度は臨時的・暫定的なものにすぎない。
上記の現状に鑑みれば,少なくとも観護措置決定を受けた少年に対して国選付添人選任権が早急に認められてしかるべきである。
よって,当連合会は,国に対して,少なくとも少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の事件全件にまで国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正を速やかに行うよう,強く求める。
2010年(平成22年)7月1日
東北弁護士会連合会 会長 熊谷 誠
- 2024-07-09New

- 再審法の速やかな改正を求める決議New
- 2024-07-09New

- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議New
- 2024-07-08New

- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明New
- 2024-05-15

- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15

- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05

- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13

- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13

- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11

- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議