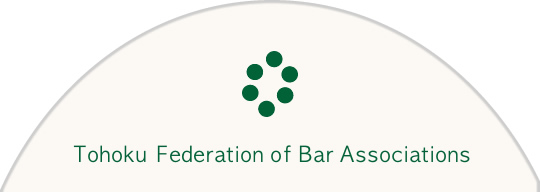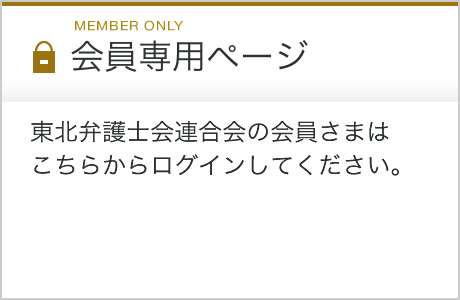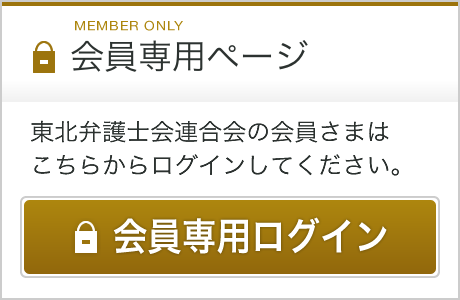司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)は、2004年12月の裁判所法の改正により2010年10月をもって廃止される。同年11月以降に採用される司法修習生は無給で修習することを余儀なくされる。その代わり希望する者に対して国が修習資金を貸与する制度(貸与制)が実施される予定である。
弁護士を含む法曹三者は国の司法制度を担い、法の支配を実現するという公益的役割を果たしている。弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としており(弁護士法1条)、各種の公共性・公益性を有する活動を行っている。したがって、弁護士を含む法曹を養成するための費用を国が負担することはその当然の責務である。それゆえ、戦後一貫して、裁判官・検察官・弁護士のいずれの道に進むかにかかわらず、司法修習生には国から給与が支給されてきた。しかるに、給費制を廃止することは国の責務の放棄であり、許されない。国民の健康と生命を守るという公益的役割を担う医師の養成においても臨床研修医の給与補助という形で少なからぬ国費が投入されている。この制度はもともと司法修習生の給費制をモデルとして作られたものであり、これとの対比からしても司法修習生の給費制の廃止は誤りである。
現在、法曹になるためには大学卒業後2年もしくは3年間法科大学院に通うことが必要である。そのため、司法修習生の半数以上は平均300万円を超える奨学金を借り、その額が1000万円を超える者もいる。加えて、厳しい就職難で就職先が見つからないまま修習を修了する者も多数出ており、司法修習生を取り巻く環境は急速に悪化している。このうえ、貸与制の導入により、新たに最大300万円を超える負債を負うことになり、経済的事情から法曹への道を断念する事態が拡大し、有為かつ多様な人材が法曹界に集まらないおそれがある。
それゆえ、上記裁判所法の改正に際しては、附帯決議において、給費制の廃止及び貸与制の導入によって「経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」が必要である旨明記された。給費制が廃止されれば、まさに上記附帯決議が危惧する事態が現実化することになる。
また、給費制が廃止された主たる理由は国の財政事情にあるが、そもそも裁判所関係の年間予算(司法予算)は国家予算の約0.4%を占めるにすぎない。三権分立の一翼を担う司法予算がこれほど少額であること自体が異常であり、国の財政を理由に給費制を廃止するのは許されない。
よって当連合会は、給費制を継続するため最大の努力を傾注することをここに明らかにし、国に対し、給費制を継続するための法改正を早急に行うことを強く求める。
以上のとおり決議する。
2010年(平成22年)7月2日
東北弁護士会連合会
- 2024-07-09New

- 再審法の速やかな改正を求める決議New
- 2024-07-09New

- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議New
- 2024-07-08New

- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明New
- 2024-05-15

- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15

- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05

- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30

- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13

- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13

- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11

- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議