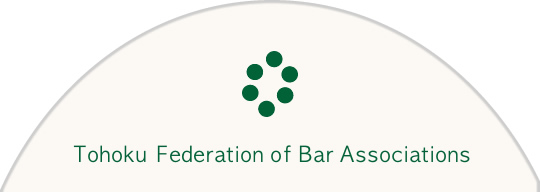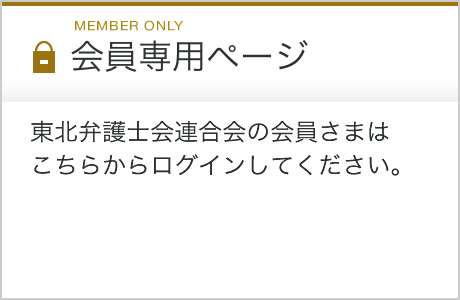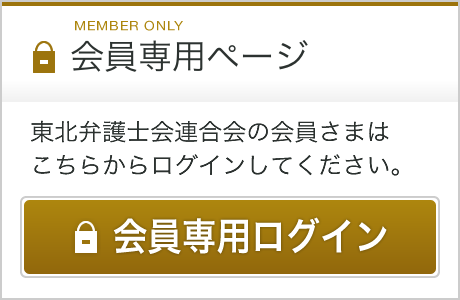東日本大震災(以下、「本震災」という。)が発生してから、被災各地では、一日も早い復旧・復興を目指して、復興計画を策定し、復興に向けた歩みを進めようとしている。その歩みは、住民の希望とは裏腹に、予算措置の遅れなどから遅々として進まない一方、ときに拙速に流れて、住民の意見が十分に反映されていないとの指摘もある。
当連合会が、2011年7月8日付けの「東日本大震災の被災者救済と被災地の復旧・復興を求める決議」において求めたように、復興計画の目的はモノの復旧ではなく、人間の復興という観点から定められるべきである。
この人間の復興という観点から見たとき、震災復興にあたっては、個人の生活基盤の確保を軸に、働く場、新しい居住の場の確保と、生活再建の支援が展開されるべきであるが、現状、以下のような問題が存在する。
まず、被災地域の住民には、新たな生活基盤が確保されるべきであるところ、災害弔慰金、義援金は避難生活の費用や被災前ローンの返済等に充てられ残っておらず、被災者生活再建支援金は、合計で最大300万円の支援しかないため、住宅再建資金としては全く足りない。また、同支援制度の申請期間は、本震災のような大災害からの復興に必要な期間には全く見合っていない。支援金の額の大幅増額及び申請期限の延長が不可欠である。
そして、個人の生活基盤を支えるのは家族であり、被災によって家族を亡くした方に対しては災害弔慰金を支給することで、これを見舞い、生活再建を支援する必要がある。しかし、災害関連死の認定に関しては地域ごとにばらつきがあり、必ずしも被災者を適切に支援できていないとの指摘もある。災害関連死に該当する可能性が高いと見られる具体例を挙げて、明確化した認定基準を定め、それを自治体に周知した上で、できる限り広く認定して弾力的運用をするよう指導すれば、被災地域毎の状況の差に基づく差異を超えるような違いは生じないはずである。
次に、生活基盤の整備には家計の正常化が不可欠であるところ、被災者の被災前のローンの処理に関して、被災ローン減免制度(正式名 個人債務者の私的整理に関するガイドライン。以下同じ。)の運用が開始され、現在に至っているが、被災者救済という目的からは問題点が多く、実効性のある、新たな法制度の整備が必要である。
そして、生活基盤を実効的に確保するには、働く場である事業所の基盤整備が必要である。現状の、東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構による債権買取とグループ補助金の制度では、被災地域の個人事業、中小零細企業の再建支援には不十分であり、その事業運営に対する一定の補助も必要である。
最後に、生活基盤の確保には、居住地や社会生活を営む場の確保が必要だが、防災集団移転促進事業の移転先や防潮堤の設置については、用地確保の場面で、相続関係が未処理のままの不動産の処理が問題となっている。既存の法制度にとらわれることなく、未曾有の大震災からの復旧・復興の場面であるという特殊な状況であることを踏まえ、状況にあった、大胆な立法措置が求められる。
以上の問題は、2013年5月28日に衆議院、6月17日に参議院で可決されて成立した「大規模災害からの復興に関する法律」でも手当てされていない事項であり、被災地域において、一刻も早い対策が求められる事項である。
当連合会は、本震災発生から2年4ヶ月が経過しようとしている今、復興の歩みの阻害要因を除去し、真に被災地の復興が促進されるために、次のとおり、新たな法制度の創設を含む制度の改正・改善を求めるものである。
1 被災者生活再建支援制度について、支給金額を少なくとも合計500万円に増額し、法定の申請期間を基礎支援金については災害発生から3年、加算支援金については災害発生から10年に延長すること。
2 災害弔慰金の支給について、災害関連死が広く認定されるように、調査すべき事実を具体的に挙げた明確な認定基準を設け、これを被災者にも明らかにするとともに、自治体に対しては基準の周知とできる限り広く認定するような弾力的な運用を指導すること。
3 被災ローンの処理について、被災ローン減免制度に代えて、被災直後から利用が可能で、中立の機関が運営を行い、かつ、その弁済計画案については法的拘束力を持つ法制度を新設すること。
4 被災地域の個人事業者、中小零細企業に対して、事業の復旧のため、使用目的を施設・設備の復旧費用に限定しない、補助金支給制度を新設すること。
5 被災地域における相続手続が未処理の不動産について、復興に資するため、迅速に自治体が購入できるようにする特別法を新設すること。
以上のとおり決議する。
2013年(平成25年)7月5日
東北弁護士会連合会
提 案 理 由
第1 はじめに
2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災(以下「本震災」という。)が発生してから、2年4か月が経過しようとしている。未だに数十万人が避難生活を余儀なくされており、復興への道のりは始まったばかりである。被災地域では、様々な復興の事業が展開されているが、その歩みは、予算措置の遅れなどの原因で、住民の意思に反して遅々として進まず、一方で、時に拙速に流れて住民の意見が十分に反映されないとの指摘を受けることもある。
当連合会は、2011年7月8日、「東日本大震災の被災者救済と被災地の復旧・復興を求める決議」において、復興計画の目的が、モノの復旧ではなく、人間の復興という観点から定められることを求めた。
この人間の復興という観点から見たとき、震災復興にあたっては、個人の生活基盤の確保を軸としつつ、個人を支える家族、家計への手当、個人の生活を支える働く場、新しい居住の場の確保と、生活再建の支援が展開されるべきであるが、以下のように、種々の問題がある。
本震災からの一日も早い復興を実現し、かつ、本震災の教訓を来たる次の災害に活かしていくためにも、直ちに新たな立法や、既にある制度の改正・運用改善をしていかなければならない。
第2 被災者生活再建支援制度の問題点
1 個人の生活基盤の確保のため、阪神・淡路大震災を踏まえて制定された、被災者生活再建支援法による支援が活用されている。
住居が全壊となった被災世帯には基礎支援金として100万円(大規模半壊世帯には50万円)が支給され、加算支援金として、①住居を建設又は購入する場合には200万円、②住居を補修する場合には100万円、③住居(公営住宅を除く)を賃借する場合には50万円が支給される(単身世帯については、それぞれその3/4。)。この支援金の支給により、被災者の生活基盤の確保、生活の再建の支援が行われる。
その申請期間は、内閣府令により、災害が発生した日から13月を経過する日(基礎支援金)及び37月を経過する日(加算支援金)までであり、都道府県が、被災地における危険な状況の継続等を踏まえ、延長することができることとなっている。
本震災では、基礎支援金は2012年4月10日までに、加算支援金は2014年4月10日までに申請しなければならないこととなっていたが、基礎支援金については2013年4月10日まで延期され、さらに2014年4月10日まで再延長された。加算支援金については2018年4月10日まで延長された。
2 被災者生活支援金の申請期間について
(1) 基礎支援金について
基礎支援金は、被災程度に応じて支給されるものであるから、被災状況が明らかになれば、直ちに申請が可能であって、申請期間は現状のままで十分であるとの考え方もありうるが、現実には、被災直後に、落ち着いて支援金の申請手続を取り得る被災者は少ないのであって、実際に、未だに申請手続をとっていない被災者、とることができない被災者が存在することから、何度も延長の措置がとられているものと思われる。
被災地での法律相談においては、未だに支援金がもらえるかどうかという相談が寄せられることもあるのだから、被災からわずか13ヶ月という申請期間が、被災地の状況に適合した期間であるとは到底言えない。
(2) 加算支援金について
加算支援金は、いずれの場合でも、契約書類等の提出が求められているから、申請するのは、建設・購入、修理、賃借が具体的に決まってからとなる。例えば、防災集団移転促進事業による高台移転の場合、移転先の買収が終わり、埋蔵文化財の調査、造成を経て、分譲となって初めて住居の建築等の準備が始まり、建築の契約書を交わした後、加算支援金の申請が行われることになる。
被災後わずか37か月でこうした事業がすべて進むことは考えにくく、これもまた、被災地の実情に合致しない期間設定だと言わざるを得ない。
(3) 基礎支援金も、加算支援金も、申請期間の延長で対応すれば足りるとの考えもあるが、それは被災者の実情を看過している。被災者は、被災による恐怖やその後の生活への不安を抱え、長い避難生活を送っているのであるから(仮設住宅での生活は避難生活の継続である。)、時期が来たら申請期間を延長すれば足りるという問題ではない。
被災者が安心して生活できるように、もともとの申請期間をより長く設定しておく必要がある。具体的には、基礎支援金については、少なくとも本震災において現在延長が決まっている程度と同程度の期間は必要であるから3年とし、加算支援金については、復興事業の進捗が順調とは言えない状況であることを前提に、高台の用地確保、埋蔵文化財の調査、造成という過程を経た上で漸く住宅の建築が可能となることも踏まえて、10年間は申請期間として必要である。
3 被災者生活再建支援制度における支援金額について
(1) 被災者生活再建支援金は、最大で、合計300万円が支給されることになるが、新たに住居を取得するのに、300万円では到底足りないことは言うまでもない。
大規模災害により、住居を失った被災者に対しては、被災前と同程度の住居を確保できるような支援がなされることが望ましいが、そのための支援金が最大で300万円では、生活基盤の確保のための支援としては不足である。
例えば、岩手県内の市町村では、加算支援金を受け取って住宅を再建する被災者に対しては、住宅再建支援制度により100万円を追加支援することとなっている。また、岩手県産材を利用した場合の支援、バリアフリー住宅に対する支援など、様々な支援制度が準備されている。
こうした支援制度の存在は、被災者生活再建支援制度だけでは、生活基盤の再建支援としては不十分であることを示しているのであって、国としての支援制度のさらなる充実が求められていると言わざるを得ない。
(2) この点,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)は、本震災発災直後の2 011年4月14日、東日本大震災に対する第一次緊急提言において、被災者生活再建支援制度の対象の拡充と支援金の増額を提言した。
震災当時政府与党を担っていた民主党でも、2011年3月29日、特別立法チームが政府に求める提言案の中で、被災者生活再建支援金の支給額を1世帯あたり最大500万円に増やす案の提言が検討されている。
また、2011年4月15日付の自由民主党第二次緊急提言でも、被災者生活再建支援金の支給額を最大500万円に増額することが提言されている。
ところが,このように、被災者生活再建支援金の増額を検討すべきとされていたにも関わらず、現状おいて何ら変わっていないことは,被災地弁護士連合会としては遺憾の極みである。
従って、被災者生活再建支援金については、せめて合計で500万円は支給されるように、早急に制度を改正すべきである。
(3) なお,直接的な支援制度に関しては、憲法29条などをあげ、「公金を私有財産の確保に使用してはならない」等と、支援金の支給が違憲であるかのように言われることもある。
しかしながら、憲法29条は、単に国民の私有財産の保護を謳い、権力が正当な理由や補償なしに私有財産を侵してはならない旨を述べているに過ぎず、同条から、「公金を私有財産の確保に使用してはならない」との内容を読み取ることはできない。
むしろ,震災によって根底から破壊された生活基盤を,被災者が自立できるところまで回復することは,憲法の基底的原理である個人の尊重原理から当然に要請されるべきものである。
第3 災害関連死についての審査基準の問題点
1 個人の生活基盤を支えているのは家族であり、家族が被災して亡くなった場合には、できる限り弔慰金を支給して、これを見舞い、生活再建を支援する必要があるとともに、被災者にとっては、災害関連死と認定されることが、家族が震災の被害者であったことの証であり、心理的に家族の死を受入れ、復興に向け気持ちを切り替える1つの要素となることから、被災後亡くなった方について、災害関連死と認定されるか否かは、大きな問題である。
災害弔慰金の支給については、市町村が判断することとなっているが、その結果、現状における申請件数に対する認定件数の割合は、岩手県で64.3%、宮城県で76.9%、福島県で86.8%(3県平均で79.4%)となっている。
地域ごとに被災状況等は異なるから、認定率が異なるという点はやむを得ない部分もあるが、宮城県、福島県と比べて、岩手県の認定率は非常に低いと言わざるを得ない。
2 認定率に差異が生じる原因については、様々な分析がなされているが、その1つとして、認定基準が曖昧であり、自治体に基準の設定が任されていることが挙げられている。
災害関連死に該当するかどうかの判定が難しい案件については、市町村又は市町村から委託を受けた県に設置された災害弔慰金支給審査委員会により判断を行う。災害弔慰金支給審査委員会は、通常、医師、弁護士等の専門家によって構成されるが、認定基準が曖昧で、自治体毎に任されていることから、例えば医師が医学的見地から因果関係を要求することで、関連死とは認定されない等の問題が生じていることが考えられる。
災害弔慰金は、損害賠償金等とは性質が異なり、遺族に対する弔意及び支援の趣旨で給付するものなのであるから、その支給対象となる災害関連死はできるだけ緩やかに認定されるべきである。災害関連死と認められ得るかどうかについて、医学的な見地から、厳格な因果関係を要求するのでは、制度趣旨にも被災地の実情にもそぐわないのであって、災害がなければ、その時期に死亡することはなかったと認められる事案については、もれなく災害弔慰金が支給されなければならない。
3 日弁連は、2012年5月11日、「災害関連死に関する意見書」において、「東日本大震災の災害関連死の実情を踏まえると、災害がなければその時期に死亡することはなかったと認められる場合を災害関連死と認めるのはもちろん、因果関係の途中に因果関係の断絶につながるような事象が若干みられたり、事実認定が困難な空白時期が若干あったとしても、災害がなくても同時期に死亡したことが確実と言えるような場合以外は、弔意の趣旨に添って災害関連死と広く認定がされるよう運用されるのが相当である」とした上で、「特に災害関連死に該当する可能性が高い例として、以下の事実に関連して、死亡し、あるいは体調を崩し、あるいは病状を悪化させ、その後震災前と同程度まで体調を回復することなく亡くなった場合等が挙げられる」として、地震及び津波、原子力発電所事故、ライフラインの断絶、避難所、避難先、仮設住宅及び被災した自宅等の住環境の変化、災害によって生じた人的環境の変化、災害によって起きた環境変化等のストレスによる自傷行為等の具体的な事実を挙げた。
これは、災害関連死が広く認定されるように具体的な事実を挙げて、認定基準を一定程度明確化するものであり、こうした認定基準がすべての自治体に周知されていれば、被災地域毎の状況の差に基づく差異を超えるような違いは生じないはずである。
4 国は、災害関連死の明確な認定基準を設け、これを被災地の自治体に周知し、被災地の自治体は被災者に認定基準を明示するとともに、できる限り広く認定するよう弾力的運用を行うべきである。そうすれば、被災者が、被災地毎に異なる認定状況により不公平感を感じることもなく、また、基準が不明確であるためになかなか判断ができずに認定までの期間が長期化することもなくなるのである。
第4 被災ローン対策についての問題点
1 被災者の生活基盤を整備するためには、被災者の家計を正常化しなければならない。
本震災で津波の被害を受けた被災者の中には、住宅や自動車が流されたが、それらを購入した際のローンだけは残ってしまったという人も少なくない。
そうした人々が、住宅を建築・購入し、自動車を購入する際、新たにローンを組む場合、従前のローンに重ねて新たなローンの支払いもするということになれば、その負担は極めて大きなものとなる。持ち家に居住していた被災者が、津波で住居を失い、借家で生活することになれば、ローンの支払いに加えて、借家の家賃も支払わなければならなくなるが、二重にローンを負う場合と同様、被災者の負担は極めて大きなものとなる。
さらに、新たにローンや賃料を負担しない場合であっても、被災により職を失う等して、収入が減ってしまえば、被災前の支払を継続することは大きな負担となる。
そうした大きな負担である被災前のローンの支払を求めることは、被災者に対して無理を強いるものであり、無理を強いられては、被災者が生活の再建に向けて進むことができない。
こうした問題に対処するため、2011年8月22日、被災ローン減免制度の運用が開始された。日弁連や各地の弁護士会が求めていた立法的な解決ではなく、あくまでも、被災者と金融機関との間の話し合いによる解決という枠組みの設定だったが、1万件の利用が見込まれ、被災ローン問題の効果的な解決策として、大きな期待の中で運用が始まり、平成23年度東日本大震災復旧・復興予備費から10.7億円が充てられている(金融庁「個人債務者の私的整理の手続き費用に係る東日本大震災復旧・復興予備費の使用について」2011年8月19日)。
2 被災3県における金融機関の債務者は、少なくとも、全体で2万3271名(法人を含む。)、そのうち住宅ローンを抱える債務者は7380名(性質上、ほぼ個人だと思われる。)が存在すると考えられる(金融庁「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額」2013年3月版)。
一方で、2013年6月14日現在、同制度の利用実績は、相談件数4280件、申出準備中376件、申出件数594件、債務整理成立件数393件にとどまっており、想定された利用件数を大きく下回る。
制度そのものは、仮設住宅居住者による利用の道が開かれ、義援金・支援金といった差押禁止財産の外に500万円までの自由財産が認められ、地震保険の家財部分について250万円まで別枠で残せる余地ができるなど、被災者に有利な形での運用改善が進んできている。信用情報への登録が回避でき、保証人は原則として請求されないことなどもあわせ考えれば、運用開始時点と比較してもかなり有用な制度となっているものと評価できる。
しかしながら、そうした有用性にもかかわらず、上記の利用件数しかないということに照らせば、同制度が、被災ローン対策の制度として、成功したとは言えない状況にあることが明白である。
3 被災ローン減免制度には、次のような問題点がある。
(1) 運用の開始の遅れと周知不足
被災前のローンの問題は、阪神・淡路大震災のときから指摘されてきた問題であり、本震災発生前から分かっていたが、何ら対策が取られてこなかったために、結局、震災発生から5か月以上が経過してから、漸く被災ローン減免制度が始まった。
しかし、その時点で、既に8000名を超える債務者が条件変更を済ませていた(金融庁「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額」2011年7月版)。その後も、周知が不足したことで、被災者の多くはこの制度の存在すら知らないまま、金融機関に対する支払を続け、又は、支払条件の変更契約を結んでいるのであり、現在では2万名近い債務者が条件変更の契約を締結してしまっている。
我々弁護士が、周知の活動を行い、また、国や地方自治体、金融機関に対して周知の徹底を求めて活動してきた結果、少しずつ利用件数は増えてきたが、当初の見込みほどに増えることは望めない。
被災前から制度が用意されており、被災直後から被災者への周知が徹底していれば、ずっと利用件数は増えていたものと言える。
(2) 運用主体の構成、運用に問題があること
個人版私的整理ガイドライン運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、銀行等からの出向者がその事務職員として運営に当っている。そのため、様々な面で、自然と、金融機関よりの判断が多くなる。その結果、例えば、ガイドラインによれば認められるはずの計画案であっても、「金融機関が納得しない」などの理由で、ガイドライン本部から計画案の金融機関への送付を断られることがある。また、登録専門家がガイドラインに則した運用を求めて様々な質問をしても、運営委員会本部における決定事項であり、理由を回答する必要はない等という対応も行われており、制度としての透明性や利用基準の明確性にも大きな疑問がある。
全くの第三者による公平な運営が必要である。
(3) 弁済計画案には金融機関に対する拘束力がないこと
弁済計画案は、登録専門家がサポートして被災者が作成し、確認報告担当の登録専門家がガイドライン適合性をチェックした上で、運営委員会から金融機関に送付されれば、金融機関は、計画案に同意することが前提となっていると説明されてきた。
ところが、実際には、金融機関は、独自の基準で和解条件を定め、被災者の弁済計画案が拒否される事例もあった。そうした金融機関の対応に対して、運営委員会は、金融機関を指導・説得するのではなく、被災者側に、金融機関が望むような弁済計画案を提出するよう求めるようになった。
さらには、手続開始前に、一定金額の支払いを認める念書を提出させたり、運営委員会の意向に従わない確認報告登録専門家を理由もなく解任し、付け替えたりもするようになり、もはや被災者支援という制度の目的が見えなくなってしまっている。
弁済計画案の内容に金融機関が拘束されない制度設計であるため、結局、金融機関の主張に則した形での和解が強要されることとなり、被災者がその生活状況、収入状況に基づき、ガイドラインに沿って作成した弁済計画案が無視されてしまうことになるのであるから、公正にチェックされた弁済計画には一定の拘束力が必要である。
4 これらの問題を解決するためには、被災直後から利用が可能で、中立の機関が運営を行い、かつ、その弁済計画案については法的拘束力を持つ制度が必要である。
例えば、個人再生手続の利用要件を緩和し、提出書類を簡易にして、申立を容易にした上、裁判所が中立公正な立場で再生計画を検討し、認可されれば、金融機関はその結果に拘束されるということにし、かつ、同手続を利用しても信用情報には記載されないこととする等の制度が考えられる。
本来制度を利用すべき多くの被災者達が、制度を知らないまま、返済を続けている状況が生じているのであるから、速やかに、立法により有効な制度を構築し、それは今後生じうる別の災害にも適用されるものでなければならない。
第5 事業者に対する支援の問題点
1 被災した事業者への支援としては、東日本大震災事業者再生支援機構又は産業復興機構による債権の買い取りとグループ補助金の制度がある。
東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興機構は、対象となる事業者について、債権者である金融機関から債権を買い取り、一部を免除するなどして、事業者の再建を図っていく支援制度である。被災前の負債については、一定程度負担すれば良くなり、運転資金等については新たな融資を受けることで、被災地における再建が可能となる。しかし、実際に融資が受けられるかどうかは不明であるし、運転資金の補助があるわけではないため、債権買取後に再建が成功するかどうかは不明である。
グループ補助金は、中小零細企業や個人事業主がグループを作り、グループの復興事業計画に基づく施設や設備の復旧費の一部の支援を受ける制度である。県と中小企業庁が審査し、地域経済、雇用、コミュニティーに役立つと認められると、復旧費の4分の3について助成を受けることができる。しかし、補助金は施設や設備の復旧費にしか充てられず、運転資金に充てることはできない。よって、グループ補助金によって施設や設備を復旧できても、実際に事業を再建できるかどうかは分からない。
2 被災者の生活基盤を実効的に確保するためには、被災者の働く場の確保が不可欠である。住居ができても、働き、収入を得られなければ、そこで生活していくことはできないからである。
しかし、事業者に対する支援は、上記の通りであり、事業者が、実際に再建し、被災地において被災者に対する雇用を提供できるかどうかは、全く分からない。運転資金にも充てられる補助金があれば、事業再建の可能性が格段に高まることは間違いない。
3 被災地で経済を支えていた商店街等は、津波により大打撃を受けた。今後、防潮堤の整備などを待って、再び、商業活動が再開されることが望まれている。しかし、被災前に、被災地域で商店を営んでいた人々の多くは、同じ地域での再建をあきらめているという現実があり、その理由の多くは、運転資金の不足である。個人事業主や中小零細の事業体は、運転資金の補助がなければ再建もままならないことが明らかとなっている。
この状況を放置していては、被災地域の経済活動の復旧もできないことになり、被災者が働く場などとても確保できないことになる。そうなれば、被災地域では被災者の生活基盤は確保されないのであるから、被災者は生活のため、別の地域での生活再建を図るしかなくなってしまう。
4 事業者の運転資金の支援については、憲法29条などの議論が問題とされる。「公金を私的財産に入れることはできない。」というのである。
しかし、地域経済や復興支援のために、事業者の運営支援を目的として公金を利用することは、被災者生活再建支援制度において論じたところと同様、憲法に抵触していないどころか,むしろ,憲法上の要請に沿うものである。
5 以上の通りであるから、被災者の生活基盤の実効的な確保のため、個人事業者、中小零細企業に対して、利用目的を制限しない補助金を支給し、事業者の再建を支援する制度を新設しなければならない。
第6 被災地の不動産の相続処理に関する問題点
1 本震災では、多くの居宅が津波被害に遭った結果、被災者は、浸水地域に嵩上げをして、住居を建設するか、防災集団移転促進事業により高台に移転することとなる。移転先用地が確保できなければ、事業は進まず、仮設住宅での生活を余儀なくされている被災者は、先が見えないまま、生活基盤が確保できない。
高台移転の結果、空き地となる浸水地域は、商業施設や公共施設、あるいは漁業関連施設の用地として利用されると見られている。もっとも、本震災では堤防も壊滅しており、現在津波被災地は津波に対して全く無防備な状態である。商業施設を建設するにしても、嵩上げして住居を建設するにしても、あまりに危険な地域であり、今後本格的にまちづくりを進めるには、防潮堤の建設が必要とされている。防潮堤も建設用地が確保できなければ、建設自体が遅れ、浸水地域は利用できないままとなり、復興が進まない。
被災地域には、先祖代々、土地を守って、その地域で生活してきたという家が多い。自宅は連綿と跡継ぎが引き継いでいるが、特に財産関係の整理もせず、相続関係の処理も行っていない家もある。代々相続が発生していても、登記簿上の所有者は数代前の所有者のままという土地も少なくない。
自治体が高台移転や防潮堤の用地として土地を買い取るには、買取り前に、現在の所有権者を確定させた上で、すべての権利者から買取りの同意を得なければならないが、そうした土地については相続関係者が数百人となることもあり、通常の相続手続を経ていては、復興事業を速やかに進めることが極めて困難である。
2 被災自治体は、用地確保にあたり、そうした相続等の問題が生じない土地を選んで購入する等の工夫もしているが、戸籍や住民票上では行方不明等までは分からず、また、元々有効な平地が少ない地域であるため、取得が難しい土地を除いて用地を準備する余裕がないという実情もある。
そこで、被災自治体は、国に対して相続関係の処理について特例法の策定などを要望しているが、国は、個人の財産権に関する問題であるとの理由で、特別な措置を執ろうとしない。
結局、被災自治体は、地元弁護士会や法テラス等と協力関係を築き、相続財産管理人、不在者財産管理人制度を積極的に利用し、また相続関係者の利害調整を弁護士に委託するための協定を結ぶなどの方法で、迅速に処理を進めようとしている。
しかし、既存の制度を積極的に利用するということにとどまるため、大幅に復興事業の進行が早まるというものではない。
3 個人の財産権についての考慮は当然重要であるが、大規模災害後の復興の場面では、迅速に復興を進めるために、正当な補償と適正な手続のもとであれば個人の権利に一定の制限が生じてもやむを得ない。
既存の制度では、自治体がすべての相続関係者を調べ、連絡を試み、意向を調査した上で、相続関係者の意向にズレがあれば弁護士による利害調整を行う等して、それでも調整がつかなければ収用の手続をとるという手順を踏む。また、調査過程で、必要が生じれば、家庭裁判所に不在者財産管理人や相続財産管理人の選任を申立て、売買の手続をとる。その場合、申立費用の一部は自治体が負担しなければならないが、自治体自身も被災していることを考えると、その負担は重い。
そこで、例えば、有価証券についての公示制度に類似する制度を作り、被災地の不動産については、①裁判所が、権利を届け出るように公告をもって催告し、一定の期間内に届出があった者のみの意思によって売却するか否かを決定できることとし、相続問題は代金の分配の場面で処理する、あるいは、②相続人の過半数の賛成で、とりあえず自治体による買取りは可能として、相続問題は買取り代金の分配という形で処理する、そして、③いずれの場合においても、売買代金を一部の相続人に交付することは問題があるから、売買代金については供託できることとし、相続の処理が終われば供託金を分配する等の時限的、特例的な立法が検討されるべきである。
ある程度、大胆な取扱いをしなければ、多くの手間や資金をつぎ込むことで被災地域は疲弊し続け、復興の事業は遅々として進まない。
4 こうした制度は、災害危険区域に指定され、自治体が買い上げる対象となる不動産についても適用すべきである。
災害危険区域の買上不動産についても同様の問題は生じうるが、被災者にとっては、使えなくなった土地の帰趨も重要な問題であり、その売却代金は新たな住居の資金や被災ローン返済の資金となるものであるから、被災者の生活基盤の確保という点で、移転先や防潮堤の用地確保の問題と何ら異ならないからである。
5 以上のとおり、スピード感をもって生活基盤の確保のための生活の場を再建するためには、不動産の相続について、被災からの復興という状況を踏まえた新制度が策定されるべきである。そして、新制度は、将来生じる別の災害にも適用できるものとすべきである。
第7 まとめ
よって、本決議案を提案する次第である。
以上
- 2024-07-09New
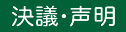
- 再審法の速やかな改正を求める決議New
- 2024-07-09New
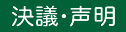
- いわれなき差別や偏見を二度と繰り返さぬよう、ハンセン病病歴者やその家族が受けた苦難の歴史を適切に記録化し、保存し、及び活用するために必要な措 置を求める決議New
- 2024-07-08New
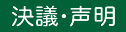
- 旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判所大法廷判決を受けて、国に対し、すべての被害者に対する謝罪と速やかな被害の全面的回復を求める会長声明New
- 2024-05-15
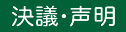
- 「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」の成立に抗議する会長声明
- 2024-05-15
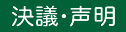
- 地方自治法改正案に反対する会長声明
- 2024-02-05
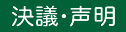
- ガザ地区での即時停戦を求め、イスラエル・パレスチナにおける紛争の平和的解決を願う会長声明
- 2023-10-30
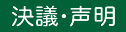
- 仙台高等裁判所の旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決を受けて、国に対し、上告の断念と速やかに全ての被害者に対する全面的救済を求める会長声明
- 2023-09-13
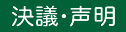
- 再審法の速やかな改正を求める会長声明
- 2023-09-13
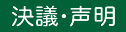
- 岡口基一裁判官の弾劾裁判につき罷免しないことを求める会長声明
- 2023-07-11
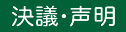
- 憲法に違反する敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有に反対する決議